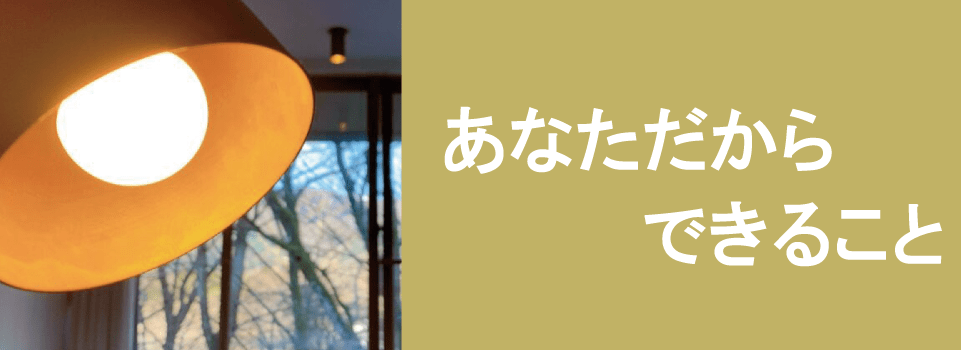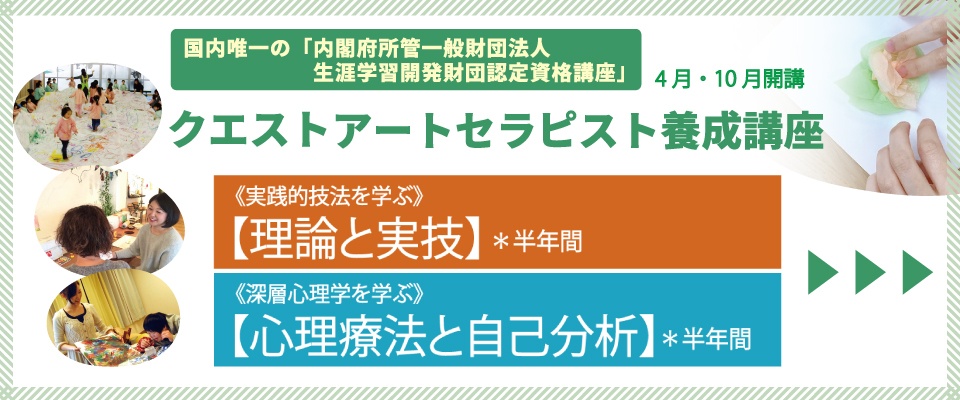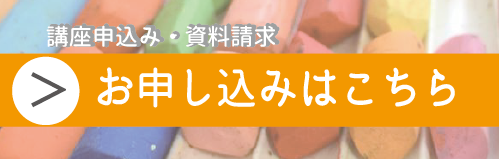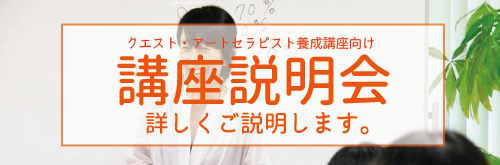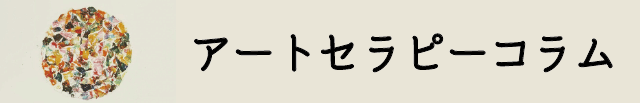アートセラピー/芸術療法(クリエィティブ・アーツ・セラピー)とは、主に欧米の精神医療の中で研究された、心のケアに役立つ心理療法です。心理的な病を持った人や、様々な障害を持つ方の治療に役立ちます。また、治療を目的としたものばかりではなく、健康な人の悩みや苦しみを癒し自己成長や自分らしさを取り戻すことにも役立ちます。
クエストでは次の講座でじっくりと学べ資格取得が目指せます。
1. 私たちの生活の中に応用することによって癒し効果を得るセラピューティックなアート(クエスト・アートセラピスト養成講座)
2.アートセラピーの柱となる3つの手法を、1回ずつにわけて学ぶ(心をケアするアートセラピー講座)
アートセラピーとは
「アートは人類の最も偉大な発明だ」という人がいます。
何故なら、言葉として表現できない心の世界(抽象的な概念)を、目に見えるかたちにして現実世界にあらわす(具体的な形を与える)もの……それがアートだからです。
アートセラピー(芸術療法)は、アート表現の「見えない心にかたちを与える力」を利用します。
その力は、私たちの心身の健康を回復させるだけでなく、健康な人をより健康にする(成長する)ことを可能にした心理療法の一技法です。
絵の具やクレヨン、また粘土や羊毛、時には自然素材を使いながら、思いのままに自分自身を表現することで、解放されたり、整理されたり、自分でも気付かなかった「本当の自分」に出会うことになります。
「アート」と言っても、何も特別なものではありません。絵のうまい・へたなどは一切関係なく、ありのままに表現するという行為そのものが大切なのです。手や目や脳の感覚を刺激することにより、鈍った五感を活性化する効果も期待できます。
アートセラピー(芸術療法)の効果
アートセラピー(芸術療法)では、「自分でも気付かなかった自分」に出会うことができます。自分の不安・哀しみ・寂しさ・喜び・楽しさなどをしっかりと把握すること(自己分析)は精神の安定にとって非常に重要で、セラピー・カウンセリングにおいて欠かすことのできない要素です。そしてアートセラピー(芸術療法)では、そのほかにも次のような効果が期待できます。
●感情の解放~カタルシス

絵を描いたり、何かをつくったり、そうやって思いのままに表現することで、心の中に抑圧されていた感情が、外の世界へと発散されていきます。
言葉では表現しきれない想い、自分でも気付いていなかった気持ち……
そういったものがアートを通して表現されることで、心が軽くなったり、気持がスッキリしていきます。
つまり、心理的な浄化(カタルシス)が起こるのです。
また、こうした経験は、私たちの創造性を呼び起こすきっかけになります。
●葛藤や混乱した思考の整理
私たちの毎日は複雑化し、日々多様な変化を求められがちです。
そのことがまたストレスとなって、ますます私たちの心は複雑化していきます。
「自分が何をしたいのか」「自分が何を感じているのか」
そういったことがわからなくなることがあります。
そういった時に、線や色や形を使って、自分の心の中を視覚化することができるのがアートです。
そうすることで、客観的に自分と向き合うことができ、葛藤や混乱した思考が整理されていきます。
●心のバランスをとる
現代社会では、どうしても言語や論理的思考を司る〈左脳〉が優位になりがちです。
本当はリラックスしたい眠る前も、スマホが手放せない方も多いかもしれません。
左脳を活性化するばかりでは、眠りも浅くなり、その眠りの浅さが、別の不調を引き起こすこともあります。
アートは〈右脳〉を活性化します。
右脳は心をリラックスさせる脳。
右脳を活性化することで、心のバランスを取れるようになると、日常に余裕がうまれます。
●好奇心 意欲の回復 リカバリー
アートセラピーは「素材のセラピー」とも言われています。
柔らかな筆感のクレヨン、ふわふわした羊毛、かたく直線的な木片、、、
さまざまな素材に直接触れ、刺激を受けることは、私たちの無意識にも心地よい影響を及ぼします。
それは、幼い頃の無邪気な心や好奇心を呼び起こし、自己回復への呼び水となってくれるのです
アートセラピーの一例「幸せ」「喜び」
下の絵はあるセラピーの時間に「幸せ」「喜び」を表現してもらった一例です。
みなさんもぜひオイルパステルや色えんぴつなどで描いてみてくださいね。
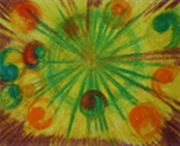
花火のように外へ外へと広がっていきます。その喜びを自分ひとりで味わうのではなく、周りにも広げていくかのようです。

じわじわとあふれていく喜びのようです。穏やかな至福の状態にも見えます。次第にそのやわらかい広がりがまわりに伝わっていくようです。

私は今こんなにうれしい!と自分で喜びをたっぷりと味わっているようです。中央にある目と大きな口がその喜びの大きさを表現していますね。

じわじわとあふれていく喜びのようです。穏やかな至福の状態にも見えます。次第にそのやわらかい広がりがまわりに伝わっていくようです。

周りがどうであれ、自分の幸せや喜びをたっぷりと味わっている様子。自分が喜びにあふれてさえいれば、その存在は周りから見てもはっきり分かりますからね。

小さな花びらがちりばめられていく様子。同じモチーフの連続は、喜びの大きさを表現しています。シャボン玉のように次々に生まれてくかのようです。
今回はテーマのあるものですが、テーマのないのもあります。
いずれにしてもアート表現は、目に見えないものを自分の内側から表現し、それを目で見ることができるようになります。
その作品への評価は一切ありません。視覚化されることは私たちの心の安定にたいへん役立ち、だからこそ癒しが訪れます。
大切なのは、あなた自身が描いた絵を、しっかりと見つめること。思いのままに描いたその絵に、あなたの心がどのように反映されているのか。じっくり絵と対話することが自分の理解につながり、心の平穏や自信を導いてくれるでしょう。
自分だけで解釈しきれない、もっと深く知りたい、という方は、アートセラピストとの時間を設けてもよいでしょう。アートセラピストは意図的にアート表現を使う、観る専門のトレーニングを受けています。
アートセラピー(芸術療法)の専門性について
アートセラピー(芸術療法)は元来、精神疾患をはじめ様々な病状に応用される専門家による高度な技術として、欧米やカナダでは、福祉、教育、司法、医療現場などで取り入れている治療技法の1つです。
誰にでも扱えるアートだからこそ、セラピーには専門的な学びが必要となるのです。それは、病状が悪化するなどアートによるリスクもあり得るからです。
カナダ・イギリス・アメリカ・オーストラリアなど海外では協会がアートセラピストを管理し、有資格の専門職として仕事を提供しています。
アートセラピー(芸術療法)の資格
JIPATTプログラムは、日本国内にいながら学べるカナダアートセラピー協会基準の講座であり、3年間の学士課程レベルまたは修士課程レベルのトレーニングプログラムを受けディプロマを取得すると、「クリニカル・アートセラピスト(臨床芸術療法士)」を名乗ることが可能となります。(2023年でプログラム募集は終了しています。)
現在日本ではそのディプロマ取得のトレーニングを受けられるのが、JIPATTだけであるため、すでに国内で活動しているアートセラピストは欧米諸国でその所定のプログラムを修了し認定された方たちだけと言えます。
なお、クエストは内閣府所管 一般財団法人生涯学習開発財団認定の
「アートワークセラピスト」のトレーニングプログラムを提供しています。
この資格は、医療的な臨床現場ではなく、自己成長を目的とした一般コミュニティで活動することのできるもので、子どもから高齢者まで、資格取得者は様々な現場で活躍しています。
アートセラピー(芸術療法)の活動現場
<JIPATT関連>
地域生活支援センター/発達障害児支援センター
放課後デイサービス/就労移行支援事業所
緩和ケア病棟/精神科病棟
精神科クリニック/産婦人科病院
小児科病棟/ダウン症児童サポート団体
ホスピス/DV回復自立支援団体
養護学校/精神作業所
<クエスト関連>
高齢者施設(有料老人ホーム/デイケア/デイサービス)
幼稚園、園児、保護者、先生
小学校、児童、保護者、教師
地域児童館開催プログラム
科学館/美術館
学童保育
企業研修
アートワークカフェ
<子ども未来研究所関連>
子どものアートセラピー教室
親向けのアートセラピー教室 他
<災害支援>
2004年10月〜新潟中越地震時の小千谷幼稚園
2011年3月〜東日本大震災後の福島県広野町
<事件被害者支援>
2000年12月〜世田谷一家殺害事件
アートセラピー(芸術療法)の表現媒体
一般的なアートセラピー(芸術療法)は、描画、造形、コラージュ、塑像、ペインティングなどを表現媒体に使用しますが、時には、詩や物語、音楽、ダンス、ドラマなどを使う事で、効果が発揮されることもあります。
完成した作品には本人がこれまで気付かなかったような深層心理や自己表現が反映されます。

それを読み解いてカウンセリングに役立てるとともに、内面にこもりがちな感情・想いを解放することで、生きる勇気や楽しみを回復させます。
「自分」という存在への理解が深まることで、確たる「自分」を形づくっていけるのです。
「クエスト・アートセラピスト養成講座」や「アートセラピー・ファシリテータートレーニングコース」においても、このようなセラピーの実践を交えながら、心理学やカウンセリング技法を伝えていきます。
「アートカウンセリング」という考え方
 アートカウンセリングは、絵や造形などによるアート表現を使ったカウンセリングです。その目的は、悩みを解消にむかわせることであったり、自分の考えを整理したり、人生の方向を見定めることであったり、「自分」というものを知ることであったり……。
アートカウンセリングは、絵や造形などによるアート表現を使ったカウンセリングです。その目的は、悩みを解消にむかわせることであったり、自分の考えを整理したり、人生の方向を見定めることであったり、「自分」というものを知ることであったり……。
言葉を使わない「アート表現」だからこそ、自分を縛っている理屈や習慣、思い込みから自由になり、新しい「もののとらえ方」や「考え方・行動力」を得ることができます。老若男女、あらゆる世代の方々が能動的に、夢中になって取り組んでくれるのもアートカウンセリングの魅力です。

- 自然に気持ちが伝わる
- 言葉は建前に傾きやすい。アートはそういった善悪とか、因果関係からクライアントを解放し、メタファー、比喩で伝えることができる
- 見えない心(思いや感覚)を形に表現することで、対話が可能になる
- 問題や悩みを変容させることができる
- アート表現を媒介とすると、クライアントの心の過程がアートに現れるので、セラピストとクライアントとの関係が安定する。

アートカウンセリングでは、評価は一切しません。ですから、絵が苦手な方も安心して受けることができます。時には描画ではなく、粘土や写真、木片など他の画材を使う場合もあります。たった一本の線で表現した抽象画であったとしてもそこにはあなたのこころが表れています。アートセラピストは出来る限り、あなたが安心して自由に表現できる場を設けますのでご安心ください。
アートカウンセリングを行うには、アートセラピストとしての知識・テクニックが必要です。クエストではクエスト・アートセラピスト養成講座やアートセラピストが提案するすぐに使えるカウンセリング技法講座で学ぶことが出来ます。
*医療機関ではありませんので、治療を目的としておりません。あらかじめご了承下さい。
アートセラピーの歴史

アートセラピーの概念は20世紀なかごろ、アメリカの精神分析家マーガレット・ナウムブルクによって生み出されたと言われています。
ナウムブルグは「芸術表現」と「精神医学」がともに「心に働きかける力」を持っていることに注目し、アートが子供や精神病患者にどのように影響するのかを研究し、多数の書籍も出版しました。
彼女自身が「アートセラピー」という言葉を考案したわけではありませんが、アートセラピーの本質的なパイオニアと言えるでしょう。その後、エディス・クレーマー博士が大学院レベルの学びに発展させました。
「アートセラピー」という言葉を初めて用いたのは、ナウムブルクと同時期にイギリスで結核患者のためのサナトリウムでアートを教えていたエイドリアン・ヒルとされています。
そのエイドリアン・ヒルのもとで働いていたエドワード・アダムソンが1946年にロンドンの精神病院でオープンスタジオ形式のアートセラピーを開催し、以降そのスタイルは多くの精神病院で行われることになりました。
アートセラピーの成り立ちにはそのほかにもいろいろな説がありますが、精神に働きかけることが目的の一つであったことは違いがないようです。
また、「アートセラピー」という言葉自体は新しくても、芸術活動を通して心を癒していく作業が古代から世界中で行われてきたことは疑いようもありません
ユングとアートセラピー

これら芸術療法の根拠となる考えを示したのが、19世紀の精神分析医カール・グスタフ・ユング博士です。
「人間の芸術表現という行為が、混乱をきたした精神の治療に役立つ」こと、また、それを自ら経験しながら、「想像と創造性からなる芸術表現が、人間の精神の統合(個人の精神的成長)に重大な働きを果たすこと」を発見しました。
ユングは、芸術表現が人間の精神の安定にとって大切な働きを果たすことを再発見したとも言えるのです.